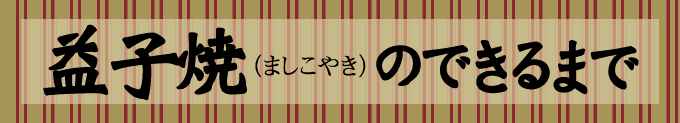
|
1.土の採掘(さいくつ)
|
2.水簸(すいひ)
|
|||
| げんりょうとなる土は、おもに新福寺のまわりでさいくつされる。さいくつされた土の中にまざったゴミなどをとりのぞく。 |  |
ゴミなどをとりのぞくため、土を水そうに入れてかきまぜる。こうするとゴミと土がわかれるんだ。 | 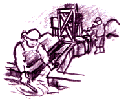 |
|
|
3.土もみ
|
4.ロクロで成形(せいけい)
|
|||
| 土の中に入っている小さなゴミやくうきを出すため土をよくもむ。土もみをすると、ゴミやくうきを出すためだけでなく、土ののびがよくなって作品が作りやすくなるんだ。 |  |
益子焼はほとんどロクロをつかって作られるんだ。 かたちのできたものは、ひかげでかんそうさせて、少しかたくしてから、またロクロにのせる。もういっかいかたちをととのえて、太陽のひかりでかんそうさせる。 |  |
|
|
5.素焼き(もとやき)
|
6.絵付け(えつけ)
|
|||
| 本焼き(ほんやき)の前に窯(かま)でやくことをもとやきというんだ。もとやきすると、えのぐなどの吸収(きゅうしゅう)をよくしたりするぞ。 |  |
ふでなどをつかって絵をかいていく。えぐは、本焼きのおんどにたえることのできる「本焼きえのぐ」というとくべつなものをつかうんだ。 |  |
|
|
7.焼成(しょうせい)
|
8.窯出し(かまだし)
|
|||
| いよいよ窯(かま)で本焼きだ。燃料には赤松(あかまつ)をつかい、だいたい1,200ど〜1,300どくらいのすごい高いおんどでやくんだ。 |  |
火をとめて、しぜんにおんどがさめるのをまって、やっと窯出し。益子焼きのかんせいだ。 | 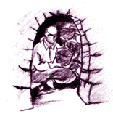 |
|
| 前のページにもどる |